
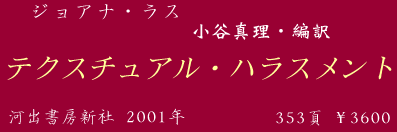
佐藤亜紀
(作家)
この手のやり口ならお任せあれ――テクハラは、たとえば次のようにやるものである。
最近ちょっと売り出し中の山形某というライターがいるのをご存知だろうか。噂話に付き合うのに一々御本を購入するほど間抜けじゃない、という方も、bk1の定期コラム(ちょっとよい子ぶった方が、本当は山形氏らしいよね)をご覧になれば充分である――そう、一番最初のページの左側、そこをずうっと、ずうっと、ずうっと下に下りてって、はい、そこです。
ちょっと不良ぶったマッチョな文章と、大層悪ぶった中身が素敵、とお考えの方もおられるだろう。実際、世評もそんなもんである。ところで、この山形氏が、実は山形嬢だということを御存知だろうか。えっ、あたしの山形様がっ、とかおっしゃる方、甘いあまい。私が知るかぎり、この種の水面 ぎりぎりライター――つまり世に名を出すべくあっぷあっぷしている辺りの、リュシアン・ド・リュバンプレ的ライターの相当数は、読者が知らないだけで、実は女だ。女名前じゃ悪口雑言の破壊力も今一だし、それじゃ兜首取ってなんぼの(ったって大抵は、池底人に挑む最低人みたいに凱歌だけ上げて去って行く、ってパターンだけど)ライター稼業としちゃ成り立たないんで男の名前を名乗るのだ。大体、下の名前が性別 不明ではないか。塩野七生みたいでしょ。本名かしらん。
さて、このヅカ的マッチョ山形嬢だが、悲しいかな、いかに益荒男ぶりを誇ってみたところで、お嬢ライターは所詮お嬢ライターである。一際マッチョを気取る瞬間に、何とも言えないわざとらしさ、何とも言えない息みが目に付くのだ。ちょっと手慣れた読み手ならすぐに見抜くことができるだろう。これは明らかに、誰か非常にマッチョ的な人物から教えられたポーズに過ぎない、と。駆け出しの頃に散々、編集プロダクションのおやじに、他のいろんなことも含めて、仕込まれたんだろうね。で、今でもそのスタイルを継続しているという訳だ。むしろ、こうも忠実にマッチョを気取り続ける辺りに、何かしら哀れなまでに女らしい、受け身な、独創性の欠落した、つまりは、真の悪口雑言ライターになるには致命的な依頼心みたいなものを感じないだろうか。世間じゃ過激で通 ってる内容だって、大方、昔の男が寝物語に聞かせたものであろう。フェミニスト嫌いなんてのは典型的な、おやじに飼いならされた女の得意技である。支離滅裂は御愛嬌。受け売りってのはそんなものだ。それを取り除いて残るのは何かといえば、何とも女性的な論理の欠落と感情論に過ぎない。
――という訳だ。
よくもまあこんなお下劣な意地悪をと感心して下さった方、私も一度やってみたいとお考えの方は、是非とも本書『テクスチュアル・ハラスメント』を御一読いただきたい。上でやった他にも手口はあるわあるは。 一応、編者小谷真理氏が序文で纏めたところにしたがって挙げておく。(p.11-12)
1. 彼女は(自分自身で)書いていなかった。(書いたのは明らかに、彼女なのに)
2. 彼女は書いたけれど、書くべきではなかった。(政治的、性的、男性的、フェミニスト的な著作だ、などの理由で)
3. 彼女は書いたけれど、何を書いたか見てみろ。(女性特有の話題しか扱っていないじゃないか、というニュアンスで。女性特有の話題を特に強調しているものも含まれる。たとえば寝室、台所、家族、女そのものといったようなことをテーマにしている)
4. 彼女は書いたが、生涯にたった一作だけだ(例『ジェーン・エア』。哀れなことに一生その一作だけだった、というような評価)
5. 彼女は書いたが、しかし本当の芸術家ではないし、本当の芸術でもない。(スリラー、ロマンス、児童文学、それにSFといったサブジャンルの作家として)
6. 彼女は書いたが、手伝って貰った。(ロバート・ブラウニング、ブランウェル・ブロンテら身内の男の助けがあったとして、評価を貶められた例)
7. 彼女は書いたが、彼女だけは(他の女性とは違う)例外的人物だ。(例 ヴァージニア・ウルフ、ただし夫レオナルドの助力はあったと言及されることあり)
8. その他(彼女は書いたが、しかし!――と、その後に一人ではなにもできないなどを暗示する何がしかの理由が来るもの)
つまり上でお見せしたのは、ほんの序の口に過ぎない。山形氏がbk1のコラムでやっているがごとく、ジョアンナ・ラスの国とは文化が違う、故に効かない、という言い方は、それこそ、検証を欠いたがさつな物言いである。ご覧の通 り、ラスの挙げた手口は効く――よしんば男相手であっても、「あいつは女」とやれば(そしてそれだけで充分以上な侮辱として通 っちゃう世の中なのは、皆さん御存知の通り。「違う、おれは男だ」と言い返されたら「え、ほんと、あんなもん書くのはてっきり女だと思ったよ」で更に駄 目押し)、充分以上に活用できる。もちろんあなた、もっと品良く、客観性を装って、溜息でも吐きながらやるんですよ。裁判なんかに引っ張り出されちゃいけません――悪口雑言業界にあっちゃ、それってただの「下手糞」の証明に過ぎませんからね。ちなみに、この犠牲者氏を、生意気の過ぎる女どもにがつんと一発食らわせて黙らせることのできる、久々に骨のある「漢」(もちろんこれは「おとこ」と読むのだ。恥ずかしいったらないね)だ、ひとつ連載でもと考えていたのに女だったとは、とか考える短絡編集者によって損害を被っては――それどころか「山形は女だ」で、ひときわマッチョな鬼畜業界から干されたりしては気の毒だから一言申し添えておくなら、私が見た山形氏は、少なくとも外見では、男性でした。もっとも、随分と華奢で声も高めだったので、生物学的に男性かどうかまでは……中身はまして……大体あんなに喧嘩が下手では……家に帰ってお袋の下着でも洗ってた方がいいのでは……あ、失礼、セクハラしちまいましたな。
これは恐るべき書物である。いや、恐ろしいのは、女の物書きが(当然、この場合は、我が国の、であるが)、薄々やられているような気がしていたが、まず99%、立件できるほどはっきりした形ではなかったので訴訟には持ち込めなかったこと、それどころか佐藤亜紀ほど明け透けなやり口ではなかったので、漠然とした違和感と不快感しか覚えなかったこと(しばしばテクスチュアル・ハラスメントは「誉め殺し」の形をとる)が、はっきりと形を取って現れることだ。正直な話、女性の物書き志願がこれを読んで萎縮することを、私としてはむしろ危惧せざるを得ない。一方、アマチュア・プロを問わず、何か書く女性は自衛のために読んでおくべきだ、とも思う――フランスの古い言い回しで、男を知ることを「狼を見る」と言うが、確かに狼どもの格好を知っておけば、姿を見るなり逃げ出すことも、運がよければ納屋から持ち出した猟銃でずどんとやることも可能だ。もちろん、積極的に、たとえば同人誌の合評会なぞで、元気よく撃ち殺していただくのが一番である。皮と引き換えに賞金を進呈と行きたいところだ。畜生、予算があればなあ。
とはいえ、ひとつ言っておかなければならないのは、私がラスの指摘の全てを受け入れる訳ではない、と言うことだ。
瑣末なところから始めるとしよう――。
たとえば、自分は女性としても別格であるとか、女性以上の存在であるとか言う主張で「女の分際」を乗り越えようとする試みについてだが、一体、男はこれをやらないだろうか。多くの男性芸術家は、自分を超男性だと、つまり、男を極めて超えた存在だと考えたがる。自称アンドロギュヌスには枚挙の暇がない。おれは特別 、その辺にいるただの男とは違う、と思い込まなきゃ、芸術家なんかやってらんないのだ。奇抜なファッションで自分をシュールな(ってのはつまり、超えてる、ってことだけど)存在に変えてしまったという点では、ダリ以上の芸術家はいないだろう。何も魔女や妖術師に身をやつした女たちや、あたしは男だと言わんばかりの女を鞭打つことはなかろう。
ジョルジュ・サンド程度の不身持ちは、当時の社交界の御婦人としてはむしろ品行方正と言わなければならない。一桁程度の男出入りは出入りの部類に入らなかった。何しろあなた、この世代のばあさん達は七十過ぎてからも「近頃の殿方は舞踏会でもキュロットをお穿きにならないので、何を考えておいでかちっとも判らない」とか言ってけらけら嗤ってた方々なのだ。ぐちゃぐちゃいうのは町人だけだ。或いはピューリタニズムに侵された後世の堅物だけだ。この場合の問題はジェンダーより、社会階層と習俗にある。
文体やトーンの一貫性の欠如は、必ずしも無教育な者や女性に特有の欠陥ではなく、むしろ固有の時代様式でありうる。ブロンテの様式の女性性を擁護する前に、同時代の様式との比較があってしかるべきではないか。ベルリオーズなんか聞いててそう思わない?
ラスの引用によれば、エリカ・ジョングは「血の滾りや根性の何たるかも知らず、娼婦と寝たり、道端でゲロを吐く気分がどんなものかなんて、到底わかりっこない……。この言葉を聞いて、女に生まれた自分を惨めに感じたものだ」と言ったそうだが、この点に関してなら、文化が違うね、とは言えるかも知れない。少なくともこの腐敗堕落した日本においては、熱血と根性は長らく少女漫画の主要なテーマで(漫画を論じる男はパスして通 るけど)体育会系の女どもは熱射病や脱水症状でひっくり返るまでグランドでウサギ跳びをさせられたものだし(鉄下駄 履いてた奴もいたよ)、中学生でさえ男を買うし(買わないとしたらそれはスタイルに合わないからだ。買わない男と一緒である)、道端でゲロを吐くなぞ、女学生にとっちゃ毎週のことである。私は東横線の渋谷―都立大間の下りホームのごみ箱に、順番にゲロを吐きながら帰ったことがある。もう一駅を制覇できなかったのは、そこで吐いてるうちに最終列車が行っちゃったからだ。渋谷のガード下で爆睡してハンドバッグなくした、って書かれて怒ってた女性作家もいたけど、その反論が、ガード下で寝たんじゃない、センター街のシャッターに凭れて寝たんだ、だったりするのだ(それでハンドバッグで済むんだから、いい国だよね、全く)。それじゃ飽き足らなくなり、第三世界をバッグパック背負ってうろうろして危ない目に遭うのも、専ら女である。だからってクイーンコングの心臓を持ったジェーン作家になれる――とはあんまり思わないが、こんなのはみんな普通 のことだ。性別を異にする作家のお寒い人生経験(真面目に一生懸命勉強していい大学に入って、在学中に、或いは院生で、或いは腰掛け程度に就職してデビュー、ってのが、我が国ではよくある男性作家のパターンである。無菌栽培とでも言いますかねえ――三十の坂をうまく越えられないのも道理だ)を哀れむのは、我が国ではむしろ女性の方である。小説において経験が全てではない(むしろ決定的な経験に足を引っ張られてろくなものを書けない人の方が多いかも)としてもだ。
ま、最後のは別として、私がこうした細かい点を指摘するのは、この種の緩い事実認識が、正当な主張を貶める口実を与えかねないからである。フェミニズムの主張は、概ねにおいては、正しい。ただ、もう少し社会学的/歴史的厳密さを持って欲しいと思うことはしばしばだ。ほんの少しリサーチの幅を広げて掘り下げれば、より正確で説得力のあるイメージが得られる筈なのに、ひどく大雑把で画一的なもので満足している場合が、特に女性史には、あまりにも多いのである。
そして何より困りものなのがこれである――女性は、女性作家の系譜の中で、女性固有の価値観に従って、数多の女性達と肩を並べ、隊伍を乱さず(つまり「おほほほほ、あたしは天才なのよ、脳味噌の足りないお引きずりどもと一緒にしないで頂戴」はなしってことだが――しかし、これなしで書くなんてことが可能なのかね)書いていかなければならないのか。それは本当に有効な手段なのか。
勿論、こうした、げっ、と言わざるを得ない、おぞましいまでに抑圧的な主張には(男が女にこれ言ったら、普通 、ビール瓶で殴り倒されてるよね)、大層進歩的な思想が背景にある――ということを、実は今日、デビッド・ロッジの小説を読んでいて知った。ものすごく分かりやすいのでちょっと引用しておく。新作『考える』の舞台、グロスター大学(仮称)に『素敵な仕事』のロビン・ペンローズ先生がやって来て(ファンの方々のために一言。ペンローズ先生は例のデリバティヴに走った男と別 れ、工場長とも別れ、いつの間に生まれたのか判らない四歳の娘を抱えて、新設大学の学科主任に成り上がっている)やる「サブジェクトを問う」という講演の内容を、この小説のヒロインが聞くのだが、
「サブジェクト」は、一種の多重の地口であることがわかった。物事を経験する個人としての主体(サブジェクト)、文の主語(サブジェクト)、国家の臣民(サブジェクト)、大学のカリキュラムにおける英文学という科目(サブジェクト)。わたしにわかった限りでは、大筋の論旨は、こうだ。こうしたすべての意味におけるサブジェクトは「悪い物」であり、古典的精神分析においてエゴが特別 扱いされたこと、伝統的文法において形式的正確さが崇められたこと、植民地主義によって、従属させられた人種が搾取され虐げられたことと、文学的規範のあいだには類似点がある。そういうことはすべて抑圧的で専制的で男性中心主義的であり、脱構築されなければならない。
なるほど、そういうことであったのか。目から鱗である。たとえばリンダ・ノチリンの「私たちの知る範囲で一流の女性芸術家(佐藤註:この場合は美術家)が輩出した例はない」という文章を引いて、一流か一流でないかは主観的判断だ、とラスが言っているのは、こうした観点からすれば理解できる。ただし、極めて否定的に、だが。
残念ながら、美術における「一流」と「二流」と「三流」の間には、個人の趣味嗜好なぞ寄せ付けない、厳然とした格差がある。これは、美術を純粋な目の快楽に還元して判断できる人間なら誰しも同意してくれることだろう。レオナルドとレンブラントとピカソは一流だが、ドラクロワとセザンヌとマティスは違う。プラド美術館で半日を過ごして、ベラスケスは冷ややかで事大主義だが確実に一流、ゴヤはショッキングであり訴えかけてくるものはあるが残念ながら三流、ということに気付かないとしたら、絵なぞ見ない方がいいのである。ある種のフェミニズム(およびポスト・コロニアリズム)の観点からすれば、男性中心主義的カノンに洗脳されていると非難されるかもしれないが、そういう方たちに対して、私は逆に聞きたいのである。
あなた方はカノンの何を知っているのか。
一流が一流であり、三流が三流であるのは、偏に、その作品が実現している精妙極まりない均衡の問題である。たとえばゴヤのように表現主義的な絵画は、他に何もしなくても、再現内容で受け手を動揺させることができる。この動揺こそ絵画の価値である人々(もちろん私は軽蔑を込めて言うのだが)にとっては確かに、これは素晴らしい絵画だろう。ところでこの均衡の問題から言わせていただくなら、ゴヤの絵というのは他愛もなく坐りがいいのである。これはドラクロワも同様だが、描かれているものの衝撃に頼って、凡庸な安定の上にあぐらをかいている。絵画における一流とは、非常に曖昧な言い方になるが、極限まで崩してなお完璧な均衡を実現することにある。そしてこの均衡こそが、六時間でルーヴルを踏破しようと絵の前を足早に通 過する人間の目に、一瞬、立ち止まらざるを得ない輝きを送り込むのであり、レオナルドの魅惑の源泉であると同時に、ルシアン・フロイドの絵にも実現されているものであり、奇跡の様な調和の中はもちろん、一見ではおよそ均衡などあり得そうにないにも拘わらず目を釘付けにして放さないところにも等しく存在するものなのだ。たとえばシェイクスピアがカノンであり、バッハがカノンであるのは、そういう意味においてである。無論、カノンとされる作品の多くは時代とともに脱落していくが(たとえば今日、サルヴィアーティは一流だがカラヴァッジォは二流だと考える者がどの程度いるだろう)、残るものは、この均衡の一点において、残る。そしてこの均衡は、よしんばその判断が「特権的集団」に委ねられており、その前に引き出されたのが「部外者」の作品であろうとも、正確に判定されるべきものなのである。無論、部外者の作品が実現した均衡が、見慣れない均衡であることはあるだろう。ただし、どこにそれがあるのかが判らない=ない、として捨て去ることは、目利きにとっては非常な恥辱である。どこかに、均衡はある筈なのだ。その均衡の一点が掴めた瞬間、それまで曖昧で掴み所のなかった見慣れない絵が、ふいに輝きを以て現れる瞬間は、同時に、価値のヒエラルキーの客観性と絶対性が確認される瞬間であり、特権的な批評家や芸術家が保持していた鑑識眼と教養が、その優越性を確認する瞬間でもある。事は結構複雑なのだ。もし、ラスが言うように、「部外者」の作品=理解不能=無価値、と判断するとしたら、辱めを受けるのは部外者ではなく、その作品を解釈しきれなかった鑑賞者たちの方であり、それこそ、彼らの価値基準の客観性と絶対性は揺らぐことになる。目利きは、目利きを名乗る以上、たとえ人類とは全く異なる身体と精神の構造を持つ地球外生命体の作ったものからでも均衡の一点を探り当て、美を搾り出してのけなければならないのだ。その程度の覚悟もない人間は、男だろうと女だろうと、白かろうと黄色かろうと黒かろうと、美の審判者の地位 を逐われなければなるまい。
ノチリンがああ言ったことは全面的に肯定できる。文句なしに一流に属する女性芸術家は、いないではないがごく少数であり、その少数も、万人が知っているというものではない(女性美術史家の皆さんは発掘と宣伝に励んでいただきたい。ただ、価値判断は厳正にね。でないと女性美術家も女性美術史家ももろともに信用を落しかねない)。ただし、悪条件にも拘わらず二流に属する女性画家が結構いるということはもっと評価していい筈だ。二流ってのは、一流じゃないってだけで、絵画としては相当のもの――ヨーロッパ美術五百年の歴史の中でも百人いるかいないか――だからね。おそらく、二十世紀全体を加えれば入れるべき女性美術家はもっと増える。この点にはどなたも賛成していただけるだろう。目下の数値上の不均衡は、女性芸術家が置かれてきた悪条件、および、「誰がこいつに評価の資格を与えたんだ?」と言うしかない男の批評家(それにしても、申し訳ないが、ラスのチョイスした男性批評家は不当に程度が低すぎないか。引用されている連中の大半は文芸評論以前、時代劇評論家レベルだ。こともあろうにジョージ・エリオットに「本当の英雄的な男が書けない」などというケチをつける、縄田一男的馬鹿を引用するのは意地悪だよ)の宦官じみた暗躍のせいだ。ま、だんだんましになってはきてますが。
ちなみに、男の芸術家のために一言弁明しておくが、彼らの主題がほぼ一貫して「ぼくのち**ん」であるのは周知の事実である。本人たちも認めている。ビルを建てても俳句を捻っても、小説を書いても絵を描いても映画を撮っても、主たる関心はそこにある。というより、彼らが作るもののほとんどが、「ぼくのち**ん」が超自然的に元気が良かったり、思い込みが過ぎるくらいぐったりしていたりする話、なのだが――それってそんなにいけないことだろうか(私に言わせりゃ、んー、可愛いね、困ったね、男の子は、ちゅっ、ってなもんである。側にいなけりゃね)。ベートーベンが俯いているのは下腹を見詰めているせいだとしても、あれだけの音が鳴りゃいいじゃないか、と思うのは間違いだろうか。ねたが何だろうと、出来がよければそれで結構なのだ。大体、「ぼくのち**ん」はけしからん、と言いながら、女の欲望について明け透けに書くのは正しい、と言うのは、何か変ではないか。
そこで次に気になるのが、ラスの描き出す悪循環の構図の真偽である。
斯様な次第で、おらあゴッホになる、的な目標となる女性芸術家ははなはだ少ない。物書きの世界においても然りであって、故に女の物書き志願は、やっぱり女って駄 目なのかしら、と思い悩みつつ、全てをゼロから始めようとする。当然、大層孤独だ。孤独から逃れるべく、あたしは他の女とは違う幻想に逃げ込み、様々な隘路にはまり込むことになる、と。
これははっきり言っていただけない。第一。目標となるような女性作家が何故いないのか、我々は最初からよぉく知っている筈である。そんなことで自信をなくすなら、最初から物なぞ書くべきではない。第二。先達がいることはそれほど大きな支えにはならないし、いないことはそれほど不利にもならない。十九世紀の初め、ユダヤ人青年が目標とするに値するユダヤ人作曲家がどの程度いたか考えていただきたい――では、同じ世紀の末には? コネの問題を別 とすれば、こんなことは何の妨げにも助けにもならないのだ。第三。ゼロから始める、というのは、ここ二百年ばかりは芸術の王道である。「僕は**先生の跡を継ぎたいんです」というのは、職人としちゃ立派だが、近代の芸術家の態度ではないし、ましてポスト・モダンな態度でもない。先行する作例との関係はもっと冷酷でないと。第四。孤独ってのは芸術家には付き物である。群れてる奴なぞろくなもんではない。嘘だと思ったら一遍、文壇バーでみんな何やってるか見物に行ったらいい。第五。「あたしは他の女とは違う」は、必ずしも行き詰まった女性芸術家特有の幻想ではない。男どもはもっと奇怪な、ほとんど笑っちゃうしかないような真似をする。第五。様々な隘路ってのは、生きてる以上は付き物ですな。何事も無駄 になんないのが芸術家の生涯ってもんだし。
しかし何より疑問なのは、女性芸術家が女性芸術家の系譜の中で、女性芸術家に囲まれ、女性芸術家らしい作品を作っていく、というヴィジョンだ。どうも、言語までが別 物でなければならないらしい。
これは絶対に受け入れられない。あまりにも不自然だ。女性作家の系譜と言うが、女の物書きが、女の書いたものだけを読み、女の書き手の影響だけを受けて育つなどということは、まず、あり得ない。意識している同時代の作家が女だけということもあり得ないし、交流がある物書きが女だけということもまずない。我々は男性作家からも影響を受け、男性作家をも意識し、男性作家とも付き合いつつものを書いていくのだ。よほど意図的に、自分の人生から男性の痕跡を消し去らない限り、先達や同僚や友人の作家が女だけ、ということはない筈である。
そして、ここに至ってぐっと詰らざるを得ないのが、この「女性特有の言語」「翻訳を経ない言語」というやつだ。
ラスの立場はよく理解できる。彼女は、女性作家が書くもの全てを認め、励まそうとしているのである。それは結構。そうした立場からは、生活経験の乏しい、どうかすると教育さえろくに受けていない女性たちが書くものも擁護しなければなるまい、ということになる。それもまた大いに結構。台所感覚とか地方主義とか話し言葉による記述とかがどうしても中心になってくるかもしれない。とすれば、その価値も主張しなければなるまい。それも結構である。
ラスの戦略も理解できる。ある種のエスニック・グループとしての戦略だ。排他的なコミューンを作り、その中でエスニック・グループ特有の価値観やライフスタイルを煮詰め、外に向って打ち出していく。やり方としては判らないこともない。
だが、私としては何とも言えない不快感を感じずにはいられないのだ――「本来の」とか「固有の」とかいう言葉によって、実際には「女性」では括りえない生きた人間に、死んだ特性を押し付けているという不快感である。昔は男が女にやっていた。今は女が女にする。こういうやり方は、もちろん下からのものだとしても、何となくスターリンの民族政策を思いださせるものがある。昨日まで混住していた人々に、別 々の、固有の言語とか文字とか習俗とかを押し付けて民族に仕立て上げていったやり方に。御期待通 り、そうやって分けられた民族同士が、いまではどかしゃか撃ちあっている。結構なことである。或いは、ヨーロッパ最大の少数民族であるロマが、自ら、泥棒であるとか人さらいであるとか称することを思い出させる。彼らはそう称することで多数派の住民を遠ざけているつもりらしいが、実際には排除や襲撃の口実を与えているに過ぎない。社会の中で男性と混住している女性が、習俗と言語によって結び付いた特殊なグループとして団結し、仲間を守り、敵に立ち向かう、という閉じた姿勢には、ある種の無理と無邪気さと無防備さがある。或いはそれは絶望から来る姿勢かもしれないが、闘争のために内部のメンバーを抑圧し、外部との無用な対立を煽り、排除の口実を与えるだけに終るのではないかという不安を感じるのだ。
エスニシティと普遍性の問題は、幾らか難しいことがある。が、エスニシティの尊重がしばしば排除の口実になっているのが、俗流マルチカルチュラリズムの現実だ。人類の文明は、異質なものを受け入れるほど成熟していない。たとえばヨーロッパの日本文学研究者が、うんざりするほど古めかしいエキゾチック・ジャパンを好む一方、現代日本文学に関しては「日本人が何故あんなものを書かなければならないのか理解できない」「西欧文明の影響が強すぎる」と言って拒絶するのは(冒頭でラスが挙げたような排除は全部やってると言って差し支えない――それこそ「猿まね」から「副次的な仕事だけ評価する」まで)、我々が木と紙で出来た家に住んで綺麗な細工物を作る愉快な小人ではないことを理解したがっていないからである。無論それに対しては、彼らの望む日本人になりきるという戦略(海外生活の長い奴が「真の国際人であるためには、まず、真の日本人でなければ」と言う時、主張しているのは実はこれである)もあるだろう。が、そういう姿勢を取り続ける限り、まともに取り組まれ、評価されることは望み薄だ。ラス的な戦略は、私の目からすれば、矢鱈顔をオークルに塗りたくり、信じられないほどけばけばしい色合いの衣服を身に着けて彼ら好みの東洋人を演じるパリ在住二十年の土産物屋店員の戦略みたいに見えるのである。はっきり言ってやった方がいいよ、「あなたがたの文明は我々を理解できる水準には達していない」ってさ。あなた好みのニッポン人であるよりは、自分の好きなように振舞って、どこまでが同質でどこからが異質なのか判断に苦しむような正体不明のアジア系でいようよ。何せ未だにイスラム系移民の扱いにさえ困ってる連中なんだぜ。媚びてどうすんの。
もう一つ、受け入れがたいのは、言語に対するあまりにも素朴な感覚である。
「物事が男性言語によって語られる彼らの縄張りから、女性が独自の言語体系を作り上げている縄張りへと足を踏み入れてみる。すると、他人から課された言語をいちいち自分の言葉に翻訳する手間が省けるという……何とも言えない解放感がある。物を考えるうえでの手間が省けたというわけではない。これまで女性たちが苦しんできた障害は、周囲の環境ではなく、翻訳という作業そのものにあったのだ」とアドリエンヌ・リッチを引用してから、ラスは言う。「『翻訳するのをやめることで』『不適切な』人々は、質の高さはもちろんのこと、真の意味で実験的な芸術を模索しはじめる」
(申し訳ないが、書き写していて幾らか寒けがしたことを御報告したい――この「真の意味で」の使い方が、何と言おうか、ガス室臭すぎるのだ。本来性への回帰なる主張は、いつだって私をぞっとさせる)
リッチも随分と問題がある。障害は環境にあったのではない、とは、環境の改善を放棄したことになりはすまいか――これは大多数の、フェミニズムを支持する女性の期待に対する裏切りだ。世の中は変らない、お前が変れ、と言う訳である。一度でいいから同じ土俵で勝負させて欲しい、と願っている(そして当然のことながら、勝負をすれば勝つと思っている)女性たちにとっては、有り難くて涙が出るようなお言葉だ。
それ以上に引っ掛かるのは、この「翻訳」という言葉である。引っ掛かるのは、リッチが語る、女性言語への回帰によって他者の言語を自己の言語に翻訳する手間が省ける、という感覚を感じたことがまるでないからであろう。「女性言語」とか「男性言語」とか言う以前に、言語そのものが常に他者のものだという感覚が、少なくとも私には、付いて離れない。この言語とかあの言語とかではない――全ての言語は、そもそも他者の言語ではないか。
非常に私的な感覚の話になるのをお許しいただきたいが、私は、よく人がやるように「母語」と言う気がしない。「母語」という語を使う人は、言葉に「国」が、つまりは国家が、人為的な機関が介入することを嫌ってそうする訳だが、私にはそれは誤魔化しとしか思えないからだ。少なくとも日本語の場合、私たちが習い覚え、教育を受け、こうやって書き始める言語は、国家による管理の色を濃厚に帯びている。崩すだけ崩していくことはできるが、根本から壊すことも、完全に私的な形に転用することもできない。できたとしても端から回収されてしまう――そういう感覚がある。故に、常に「母国語」だ。国家が制定し、管理する極めて人為的な言語であることを明示しておきたいのである。
ところで、たとえば方言で書いたとしたら自由になることはできるだろうか。これもまた不可能だ。私は方言では育っていない。幼稚園に行ってから仕方なく覚えた共同体の言語だ。おまけにこの方言の音は、日本語の表記体系では完全には再現できないと来ている。つまり、私に本来の言語などないのである。全ての言語が外国語であり、他者の言葉だ。日本語で話している時も、原―言語を日本語に解きほぐしながら話すようなもどかしさが付き纏って離れない。本来の言語に戻れば自由になれる、というような楽観的な希望は、私にはない。
むしろことは全然逆ではないか。小説は、他者の言葉と他者の声で書くものだ(自分自身でさえ、そこでは他者だ)。当然のことながら、言語もまた、他者のものであるだろう。それをはっきり認識することによってはじめて、書き手は言語的な自由を獲得する。つまり、何かの言語に「根」を求めることを断念し、何の本来性もないただの道具として扱ってはじめて、言語を意識的に操作することが可能になる。言語表現における自由は、使用する言語の外側に立ってはじめて可能になる、と言うことになるだろう。 最良の作家は常に亡命者であり、最良の作品は常に読み人知らずである。私が抵抗を感じるのは、作品を書き手に結び付け、書き手を性別 や人種や国籍に結び付け、そこから解釈や評価を引き出そうとする姿勢だ。テクストの価値を女性が書いたものであるがゆえに貶めようとする人々と、女性が書いたものであるがゆえに高く買おうというラスの姿勢は、全く同じだ。いずれにせよ、女性の書き手にとって、そうした形で作品を読まれることは致命的なのである。
ある種の女性の誠実な取り組みが、既に外側から抑圧や排除に曝されている女性作家を、今度は内側から抑圧し、排除するのではないか、という危惧は否めない。ラス的な戦略は、現に水準以上の仕事をしながら正当な評価を受けていない女性作家にとっては何の助けにもならないのだ。それとも、まさかあなた、「評価されていないのは女の言葉で女の書くべき内容を書かないからだ。お前が書いているのは男の猿真似であって、真の芸術ではない」とおっしゃるつもりでは? それってあっしらもう、うんざりするほどやられてきたんですがね。