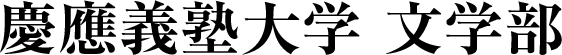- ホーム
-
教員
教員Faculty
11件
仏文学専攻
- 1
名前/職位
専攻/専門領域/研究内容
-
 芦野 文武Ashino, Fumitake准教授ashino@keio.jp
芦野 文武Ashino, Fumitake准教授ashino@keio.jp仏文学専攻
発話意味論、語彙意味論 (フランス語,日本語)「多義語」(主に動詞・形容詞・前置詞・接頭辞)の意味的同一性とヴァリエーションの記述を主要問題に据え、以下のテーマを目下の研究課題にしています。
・現代フランス語の前置詞・接頭辞の体系的記述
・現代日本語の格助詞の体系的記述
・フランス語・日本語のディスコースマーカーの意味論的記述 -
 市川 崇Ichikawa, Takashi教授ichikawa.z8@keio.jp
市川 崇Ichikawa, Takashi教授ichikawa.z8@keio.jp仏文学専攻
現代フランス文学及び思想20世紀のフランス文学および思想を主な研究対象としています。ジョルジュ・バタイユ、モーリス・ブランショ、ジャン=ポール・サルトルらについてのミシェル・フーコー、ジャック・デリダらの考察を参照しながら、実存主義が構造主義、ポスト構造主義によって乗り越えられて行く過程について考察しています。最近は、1980年代のジャン=リュック・ナンシーの共同体論に焦点を絞り、ナンシーによるバタイユ読解の射程やブランショの共同体論との差異について考えています。
-
 上杉 誠UESUGI, Makoto助教
上杉 誠UESUGI, Makoto助教仏文学専攻
19世紀フランス文学19世紀フランス文学、とりわけスタンダールを対象に小説、伝記、自伝、旅行記、政治論、芸術批評といったジャンルの作品の読解に取り組んでいます。古代ローマ人、芸術家像、チチスベオの習慣、王政の原理、軍人の理想といった主題を通してあらわれる「名誉」の概念を取り上げながら、19世紀の作家たちが過去から継承した主題や理想をいかに変容させたのか検討しています。
-
 大嶌 健太郎OOSHIMA, Kentaro助教ken.oshima830@keio.jp
大嶌 健太郎OOSHIMA, Kentaro助教ken.oshima830@keio.jp仏文学専攻
近代フランス文学(マルセル・プルースト)主にはマルセル・プルーストを研究テーマとしています。他方で、プルーストと、周辺の作家たち(ブールジェやジッドなど)との比較研究を通して、当時の文学者たちにとって“読まれること”とは何を意味し、読者とはいかなる存在であったのかという問題について考察しています。
-
 喜田 浩平Kida, Kohei教授kida@flet.keio.ac.jp
喜田 浩平Kida, Kohei教授kida@flet.keio.ac.jp仏文学専攻
フランス語学主にフランス語を対象とし、意味論と語用論の境界領域の諸現象を分析しています。レトリックや翻訳学にも関心があります。
-
 竹中 公二TAKENAKA, Koji助教
竹中 公二TAKENAKA, Koji助教仏文学専攻
16世紀フランス文学専門はフランス・ルネサンスの文学で、主にモンテーニュとラ・ボエシーを研究しています。当時の思考の枠組みのひとつであった修辞学の観点から、作家が模倣を通じてどのように文学的な個性を表現しようとしていたかを考察の出発点にしています。方法論的な問題として、読むことにおけるアナクロニスムにも関心があります。
-
 築山 和也Tsukiyama, Kazuya教授tsukiyama@keio.jp
築山 和也Tsukiyama, Kazuya教授tsukiyama@keio.jp仏文学専攻
19世紀フランス文学ボードレール、ユイスマンスの美術批評を主要な研究対象として、「超自然主義」の系譜に関心をもっています。
-
 西野 絢子Nishino, Ayako教授ayani@keio.jp
西野 絢子Nishino, Ayako教授ayani@keio.jp仏文学専攻
現代フランス文学・日仏演劇交流20世紀前半、劇場における諸芸術(劇・音楽・舞踊)の統合を試みたポール・クローデルが、能・歌舞伎など日本の伝統的な楽劇から受けた影響について研究しています。また、能をめぐる日仏の演劇交流の歴史にも関心を抱いています。
-
 ブランクール ヴァンサンBrancourt, Vincent訪問教授(招聘)vbrancourt@hotmail.com
ブランクール ヴァンサンBrancourt, Vincent訪問教授(招聘)vbrancourt@hotmail.com仏文学専攻
フランス文学Récemment, parmi les question qui m'intéressent, je me suis notamment attaché à m'interroger sur la manière dont dans des œuvres de dramaturges modernes ou contemporains comme Giraudoux ou Koltès l'espace scénique se mue en espace imaginaire et la façon dont ces auteurs intègrent dans leur dramaturgie une réflexion sur le statut de cet《espace imaginaire》, en particulier autour de la question de la fascination.
***
Recently, my attention has been drawn into the work of modern and contemporary playwriters such as Giraudoux or Koltès, in particular reflecting upon how the stage space morphs into an imaginary space as well as how these authors include in their dramaturgic compositions, a reflection on the status of this “imaginary space”, notably focusing on the fascination aspect. -
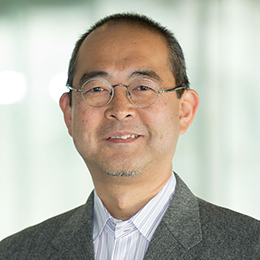 岑村 傑Minemura, Suguru教授sugurum@keio.jp
岑村 傑Minemura, Suguru教授sugurum@keio.jp仏文学専攻
近現代フランス文学20世紀の作家ジャン・ジュネの研究に軸足を置いていますが、ほかへの興味も尽きません。刑罰制度の表象については身を入れて調べていますし、「三面記事」、「帰還」、「告白」、「描写」など、ひとつの主題をめぐって複数の作品を読み解いていくことにも愛着をもっています。
-
 森元 規裕MORIMOTO, Norihiro助教
森元 規裕MORIMOTO, Norihiro助教仏文学専攻
17世紀フランス文学・思想近世フランスにおける活版印刷術の発展に伴い、「書物」という媒体がいかに作家の思考や技法を規定したかを考察しています。具体的には、神学や法学といった学知、あるいは論理学、修辞学、詩学といった諸学芸の伝達様式がどのように変化したかに関心があります。ルイ14世の孫の傅育官でもあったカンブレ大司教フェヌロンと教会史家クロード・フルリを主たる研究対象としています。