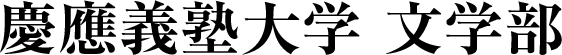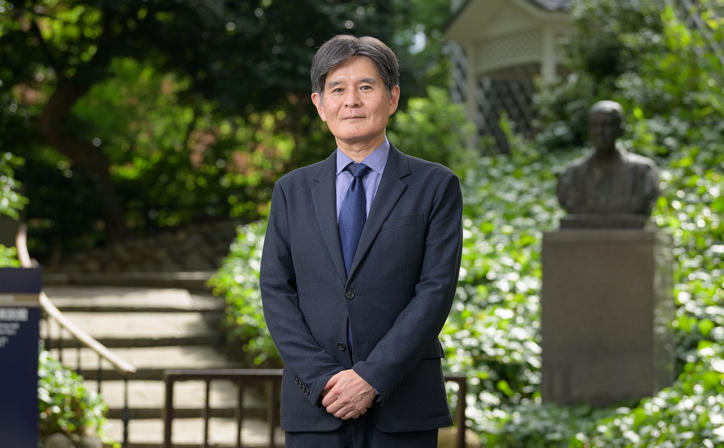
慶應義塾大学文学部(Faculty of Letters)は一般にイメージされる「文学部」とは性格を異にする学部です。私たちは「文(Letters)」を広く「学芸」(学問・芸術・科学)全般を包含する「知」を意味する語として捉えています。「文学部」での学びとして一般にイメージされがちな文学や言語学に向き合う分野ばかりでなく、人文社会科学ひいては自然科学に及ぶ多様な分野の集合体である点。それが本学文学部の最大の特徴です。
国内外問わず、今日世界中の大学の研究・教育は、ギリシャ哲学と一神教の世界観に根ざす西欧近代科学によって体系作られており、事象の区別による専門分化を志向するという特徴を持ちます。それだけに、上記の特徴を持つ本学部に対しては、なにやら具体性に欠き、掴みどころない学部という印象を抱く方もおられるかも知れません。しかしながら、今日、学問の専門分化が行き詰まりを迎えているのも事実です。
例えば、西欧近代科学では、動物を研究対象とするのは動物学、人間を扱うのは人類学と区別されます。この背後には、動物と人、自然と文化を対置する二分法的な思考が存在するわけですが、実のところ両者は分かち難く結びつき、相互に影響し影響され合う関係にあり、包括的に調査・研究しなければならない対象でもあります。また、北米北西沿岸の先住民が自らの出自を動物と結びつけて考えているように、私たちの種には異なる事象間に繋がりを見出す感性、流動的知性も備わっています。
凡そこの世界に存在する事象が多くの生物・無生物が複雑に絡み合う「万物照応」とも呼ぶべき様相を呈していることにも鑑みれば、私たちは、異なる事物・事象に繋がりを見出す流動的な知性も呼び覚ますべきでありましょう。幅広い学問分野を内包し、日常的に領域横断的な対話や議論も交わされている慶應義塾大学文学部は、専門知のみならず総合知も育む学部であると自負しています。「半学半教」を重んずる自由な学風の中、本学部で学ぶ皆さんは、専門性を深められると同時に、多角的かつ包括的な視野も育めるはずです。
5学系17専攻・2部門が提供する学びの自由
慶應義塾大学文学部では、「人文社会学科」の一学科制を敷き、その下に5つの学系と17の専攻(哲学系: 哲学、倫理学、美学美術史学/史学系: 日本史学、東洋史学、西洋史学、民族学考古学/文学系: 国文学、中国文学、英米文学、独文学、仏文学/図書館・情報学系: 図書館・情報学/人間関係学系: 社会学、教育学、心理学、人間科学)、さらに自然科学と諸言語の2部門を置いています。関連する大学院としては、文学研究科および社会学研究科があります。本学部には、学内10学部中、理工学部、医学部に次ぐ数となる150名余りの専任教員が所属しています。各教員は独創的な研究活動を活発に進め、それぞれ国内外の専門分野で注目を集める成果をあげています。
学部の定員は一学年800名。1年生は専攻を特定することなく入学し、広々とした日吉キャンパスで、多様な学問分野に触れ、幅広い教養を習得するとともに、「知」の基盤をなす語学の習得に努めます。2年以降は伝統ある三田キャンパスで17専攻のいずれかに所属し、専門的な研究に取り組みます。文学部を特徴付ける教育の形態としては、少人数教育をあげることができます。ゼミ(研究会)や各種演習科目など、三田キャンパスで開講される授業科目の多くが小規模であるため、教員と学生、さらに学生同士の間には緊密な関係が築かれます。
慶應義塾大学文学部の伝統と革新性
建学者の福沢諭吉が残した「自我作古(じがさっこ)」という言葉は、今日なお慶應義塾が大切にする信条の一つです。「我より古を作す(われよりいにしえをなす)」と読むこの言葉で福澤は、如何なる困難や試練が待ち受けていようとも、勇気と使命感を持って、前人未踏の新しい分野に挑戦せよと訓じました。
今日、私たちは、地球環境の悪化や、国や地域を超えて進むグローバル化、さらにはAIの発達に伴って生じる新たな社会問題など、既存の知識や仕組みでは対応しきれない数多くの難題に直面しています。新型コロナウィルス感染症により対面での活動が制限される状況に陥ったことは記憶に新しいところですが、今後も環境や社会に如何なる変化が生じるかわかりません。そのような時代に生きる私たちは、人間・社会・自然などに対する総合的な知識と、論理的かつ柔軟な思考力を身につけなければなりません。
過去から現在に至る人・社会・自然を扱う多様な分野を抱え、既存の学問体系の脱構築も目指す慶應義塾大学文学部は、激動の時代に挑むために必要な知識と能力を提供できる学部であると自負しています。その意味で、本学部は、1890(明治23)年の創設以来130年以上もの長きに亘る伝統をもちつつも、革新的な学部とあるといえます。