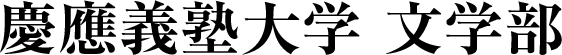- ホーム
-
教員
教員Faculty
9件
美学美術史学専攻
- 1
名前/職位
専攻/専門領域/研究内容
-
 青野 純子AONO,Junko教授
青野 純子AONO,Junko教授美学美術史学専攻
西洋美術史17〜18世紀オランダ美術史を専門とし、近世ヨーロッパの絵画市場研究にも取り組んでいます。とりわけ、18世紀以降の国際的な絵画市場と美術コレクションにおける17世紀オランダ絵画の受容と評価に関心を持っています。近年は、17世紀オランダ絵画を模写した18世紀の水彩の複製素描を調査・研究するとともに、ヨーロッパ美術におけるコピー/複製をめぐる問題について、制作と理論の両面から幅広く考察しています。
-
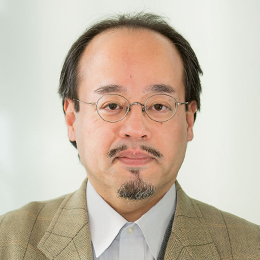 金山 弘昌Kanayama, Hiromasa教授hkanayama@keio.jp
金山 弘昌Kanayama, Hiromasa教授hkanayama@keio.jp美学美術史学専攻
西洋美術史美術史専攻ながら、主な研究分野は16・17世紀イタリア建築史です。また版画や彫刻も研究テーマとして取上げてきました。近年の関心は、ガリレオの事例に代表される、17世紀当時の科学と美術・建築との相関性です。
-
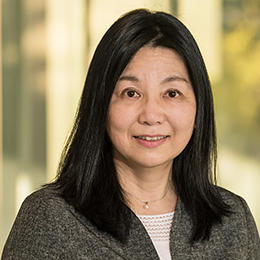 後藤 文子Goto, Fumiko教授goto@flet.keio.ac.jp
後藤 文子Goto, Fumiko教授goto@flet.keio.ac.jp美学美術史学専攻
西洋美術史ドイツ近代美術を中心として研究に取り組んでいます。とりわけ19世紀から20世紀への転換期ドイツにおいて社会変革思想と感性的創造行為が独特な仕方で接合した様相を重視し、美術、建築、庭園(造園、庭づくり)、デザイン、さらに身体運動(ダンス、体操)等の相互関連性について芸術学・デザイン学の立場から検討しています。20世紀初頭からドイツ国共和制期の芸術状況が近年の研究における重要な検討対象です。
-
 佐々木 康之SASAKI, Yasuyuki准教授ssk0811@keio.jp
佐々木 康之SASAKI, Yasuyuki准教授ssk0811@keio.jp美学美術史学専攻
日本美術史日本の古代、中世仏教彫刻史を専門とし、主に平安時代の浄土教彫刻を研究対象としてきました。彫刻作品単体だけでなく、それを置く場を構成する絵画、工芸の各種表現や、さらには観者との関係に強い関心があります。また、美術館勤務の経験から、彫刻や工芸作品の展覧会での見せ方についても、一緒に考えていきたいと思います。
-
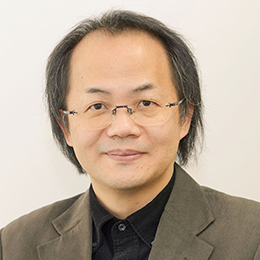 内藤 正人Naito, Masato教授naito@keio.jp
内藤 正人Naito, Masato教授naito@keio.jp美学美術史学専攻
日本美術史日本の近世期、江戸時代の絵画史と版画史が専門で、とくに浮世絵や琳派などの作品や作者が主要な研究対象です。このほか、物語絵や風俗画の系譜に連なる古代・中世から近・現代までの絵画作例全般についても、強い関心を抱いています。さらにその先にある問題として、世界の美術史における日本美術の位置付け、という大きなテーマにも取り組んでいます。
-
 中尾 知彦Nakao, Tomohiko教授nakao@flet.keio.ac.jp
中尾 知彦Nakao, Tomohiko教授nakao@flet.keio.ac.jp美学美術史学専攻
アーツ・マネジメントアーツ・マネジメント、すなわち、オーケストラ、オペラ、劇団、ダンス・カンパニー、美術館等の芸術組織のマネジメント(=経営)の調査研究と教育に取り組んでいます。日本でも他国でも、芸術組織の多くは非営利あるいは公共の組織となっていることが多く、非営利の芸術組織を中心とした研究ということもできます。
-
 西川 尚生Nishikawa, Hisao教授nishikawa.z3@keio.jp
西川 尚生Nishikawa, Hisao教授nishikawa.z3@keio.jp美学美術史学専攻
音楽学、西洋音楽史W. A. モーツァルトを中心とする古典派音楽の研究。モーツァルトの手稿譜の調査を通じて、作品をめぐる諸問題(成立過程、演奏実践、同時代の受容等)を解明しようと考えています。18世紀のウィーンとザルツブルクにおける宮廷楽団、劇場、公開演奏会、楽譜出版についても研究を進めています。
-
 福田 弥Fukuda, Wataru教授wafukuda@flet.keio.ac.jp
福田 弥Fukuda, Wataru教授wafukuda@flet.keio.ac.jp美学美術史学専攻
音楽学、西洋音楽史19世紀ロマン主義の作曲家フランツ・リストの音楽、とりわけ宗教的作品が研究対象です。残された手稿譜や書簡などから、作品の成立過程、稿と編曲の関係、さらに作品を取り巻く環境などの解明に取り組んでいます。
-
 望月 典子Mochizuki, Noriko教授nomoc@keio.jp
望月 典子Mochizuki, Noriko教授nomoc@keio.jp美学美術史学専攻
西洋美術史・芸術学17世紀フランス美術史・美術論。ニコラ・プッサン研究を中心に、プッサンの作品を規範として掲げた17世紀後半の王立絵画彫刻アカデミーにおける美術理論の確立とその変容に関心を持っています。画家の制作論、実際の作品とその受容、作品や画家を巡る言説、社会的文脈、美術コレクションなど、相互に絡み合う様々な要因を考察に加え、研究に取り組んでいます。