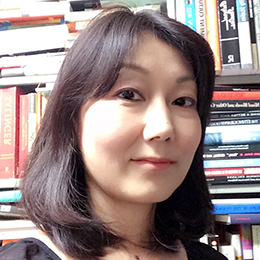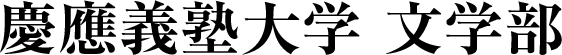- ホーム
-
教員
教員Faculty
18件
英米文学専攻
- 1
名前/職位
専攻/専門領域/研究内容
-
 井口 篤Iguchi, Atsushi教授a-iguchi@flet.keio.ac.jp
井口 篤Iguchi, Atsushi教授a-iguchi@flet.keio.ac.jp英米文学専攻
中世英文学 (14-15世紀のラテン語・中英語宗教散文)14世紀から15世紀にかけてイングランドで書かれた宗教文学について研究しています。中でも、ラテン語で書かれた宗教作品がどのように俗語である英語に翻訳され受容されたのか、そしてその過程でどのような神学議論が俗語読者たちの間に広がったと考えられるのかについて興味を持っています。
-
 大鳥 由香子OTORI, Yukako准教授
大鳥 由香子OTORI, Yukako准教授英米文学専攻
歴史学 アメリカ研究 子どもの歴史 リーガル・ヒストリー 法と人文学主にアメリカ合衆国をフィールドに、「子どもであること(Childhood)」の歴史的変遷に関する研究をおこなっています。19世紀末から1920年代にアメリカ合衆国に渡った新移民の子どもたちのケースを読み解き、子どもの越境をめぐる法制度がどのように形成されたのかを明らかにしてきました。
-
 加藤 有佳織Kato, Yukari准教授
加藤 有佳織Kato, Yukari准教授英米文学専攻
アメリカ文学、カナダ文学アメリカ文学とカナダ文学の相互交渉や、アメリカ・カナダ・日本の太平洋横断的文化交流について研究しています。また、カッパの表象文化史にも関心があります。
-
 坂本 光Sakamoto, Hikaru教授hikaru.sakamoto@keio.jp
坂本 光Sakamoto, Hikaru教授hikaru.sakamoto@keio.jp英米文学専攻
近現代イギリス文学18世紀から20世紀初頭にいたる小説作品、特にゴシック文学 (恐怖文学) を研究しています。
-
 高橋 勇Takahashi, Isamu教授isamut@flet.keio.ac.jp
高橋 勇Takahashi, Isamu教授isamut@flet.keio.ac.jp英米文学専攻
近現代イギリス文学、ファンタジー文学特に18〜19世紀の詩と韻律論、および中世主義、またそこから派生した現代ファンタジーなどに興味があります。
-
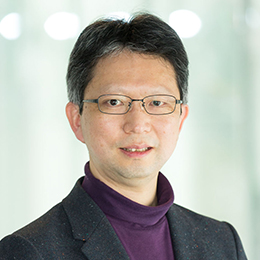 高橋 宣也Takahashi, Nobuya教授nobuya@flet.keio.ac.jp
高橋 宣也Takahashi, Nobuya教授nobuya@flet.keio.ac.jp英米文学専攻
近代イギリス文学ロマン派から20世紀初めにかけてのイギリス文学と音楽との関わり合いに関心があります。具体的には、ロマン派の詩における音と音楽のイメージ、シェイクスピアと音楽の影響関係、ワーグナーとイギリスの関係、G・B・ショーの音楽評論家としての活動などに注目しています。また、翻訳としては、ワーグナーのオペラ《ニーベルングの指環》についてのショーの独創的なコメンタリー、ナチスによるモーツァルトのイメージ操作の研究、20世紀を代表する指揮者ブルーノ・ワルターの伝記、20世紀イギリスの主要作曲家レイフ・ヴォーン・ウィリアムズの伝記などを手がけています。
-
 辻 秀雄TSUJI, Hideo教授tjhideo@keio.jp
辻 秀雄TSUJI, Hideo教授tjhideo@keio.jp英米文学専攻
アメリカ文学アーネスト・ヘミングウェイ、ラルフ・エリソン、ジェイムズ・ボールドウィンを中心に、20世紀のアメリカ文学・文化を研究しています。
-
 徳永 聡子Tokunaga, Satoko教授satonko@keio.jp
徳永 聡子Tokunaga, Satoko教授satonko@keio.jp英米文学専攻
中世イギリス文学、書物史、書誌学中世後期イングランドにおける書物文化について研究を進めています。
-
 橋本 良一HASHIMOTO, Ryoichi助教ryoichi.hashimoto@keio.jp
橋本 良一HASHIMOTO, Ryoichi助教ryoichi.hashimoto@keio.jp英米文学専攻
近現代イギリス文学、詩と詩学19世紀イギリスの詩、特にアルフレッド・テニスンの詩を研究対象としています。詩学や引喩、翻訳、ノンセンス文学などに関心がありますが、特に詩における反復に興味があり、博士論文ではテニスンの詩における反復を扱いました。
-
 バナード ピーターBERNARD, Peter准教授
バナード ピーターBERNARD, Peter准教授英米文学専攻
日本近代文学、比較文学、幻想文学、ゴシック論近代英米文学と日本近代文学における「田舎ゴシック」言説を研究対象として、泉鏡花やM・R・ジェイムズ、H・P・ラヴクラフトについて研究しています。また、近代日本におけるゴシック翻訳論という視点から日夏耿之介にも関心があります。
-
 細野 香里HOSONO, Kaori助教kaorihosono@keio.jp
細野 香里HOSONO, Kaori助教kaorihosono@keio.jp英米文学専攻
19世紀アメリカ文学・文化マーク・トウェイン(1835–1910)を中心に19世紀アメリカ文学を研究対象としてきました。最近はジョージ・リッパード(1822–1854)らによる南北戦争以前の扇情主義的文学作品における拡張主義の研究に取り組んでいます。
-
英米文学専攻
英語史、歴史言語学古英語から現代英語にかけての言語変化の諸相、および英語史の記述に関心があります。とりわけ言語変化の how と why を探ることに興味があります。なぜ英語の名詞複数形に -s がつくのかという疑問に目覚めてから何年も経ちますが、言語は不思議だらけですので、疑問が次から次へ湧き出てきて尽きることはありません。最近は REcord(名詞)と reCORD(動詞)のペアなどが示す「名前動後」の強勢パターンの歴史的発展や英語綴字史に関心を寄せています。
-
 若澤 佑典WAKAZAWA, Yusuke准教授yusuke.wakazawa@keio.jp
若澤 佑典WAKAZAWA, Yusuke准教授yusuke.wakazawa@keio.jp英米文学専攻
18世紀イギリスの文学・文化、スコットランド啓蒙思想、会話/対話としての哲学学部ではイギリス経験論やアメリカン・プラグマティズムといった英語圏の思想史を学び、「共感」や「驚き」といった日常生活の言葉でものを考え、書くことの重要性を実感しました。大学院からは、文学と哲学が交差する18世紀イギリスの言語空間にとりわけ魅せられ、専門分野としてきました。ポスドク以降は「おしゃべりの文化」から18世紀イギリスの文学・思想・絵画についてずっと考えています。とりわけ、会話・社交する存在としての人間像を提示し、当人もお話し好きだった哲学者/歴史家/文筆家デイヴィッド・ヒュームの著作や書簡が研究の主軸です。プロジェクト研究では18世紀東アジアの専門家たちと協働し、「グローバルな18世紀世界」像の構築を目指しています。