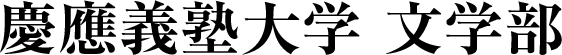- ホーム
-
教員
教員Faculty
名前/職位
専攻/専門領域/研究内容
-
 喜田 浩平Kida, Kohei教授kida@flet.keio.ac.jp
喜田 浩平Kida, Kohei教授kida@flet.keio.ac.jp仏文学専攻
フランス語学主にフランス語を対象とし、意味論と語用論の境界領域の諸現象を分析しています。レトリックや翻訳学にも関心があります。
-
 木下 衆KINOSHITA, Shu准教授shukinoshita.soc@gmail.com
木下 衆KINOSHITA, Shu准教授shukinoshita.soc@gmail.com社会学専攻
医療社会学、社会調査法、家族社会学私はこれまで高齢者介護、特に認知症患者の方への介護を中心に、研究を進めてきました。認知症患者ご本人、そのご家族、介護・医療専門職の方々との間の相互行為の展開を、社会学的な観点から分析しています。
-
 金 柄徹Kim, Byungchul教授kim@keio.jp
金 柄徹Kim, Byungchul教授kim@keio.jp諸言語部門
韓国語、文化人類学倭寇・家船・海民の歴史と文化、現代韓国における家族の変容、在日コリアンの教育とアイデンティティ、韓国の徴兵制と認識の変容などを研究してきました。最近は、植民地と戦争の記憶、アジアの食文化(特に、仏教と肉食)についても研究しています。
-
 粂川 麻里生Kumekawa, Mario教授mario@myad.jp
粂川 麻里生Kumekawa, Mario教授mario@myad.jp独文学専攻
近現代ドイツ文学、文化史、スポーツ史、ポピュラー音楽、怪獣映画ゲーテが、20世紀の思想家たちに与えた影響の研究を出発点に、「言語」、「形」、「色」、「音」、「時間」、「身体」、「自然」といった諸概念の関り合いについて考察しています。それと関連して、アーカイヴ学、ポピュラー文化・音楽論、怪獣映画論、サッカーやボクシング等の近代スポーツとドイツ独自のトゥルネンをめぐる文化史も研究しています。
-
 倉石 立Kuraishi, Ritsu准教授kuraishi@keio.jp
倉石 立Kuraishi, Ritsu准教授kuraishi@keio.jp自然科学部門
発生生物学イトマキヒトデの胚や幼生は透明で単純な形をしているため、生きたままで体を構成するほとんどすべての細胞を観察したり、それらに対して除去や移植などの顕微手術を施すことが出来ます。私はこのような材料の特質を生かして、胚や幼生を構成する各部分が発生の進行や生命の維持にどのような役割を果たしているか、解析を進めています。
-
 越野 剛KOSHINO, Go教授
越野 剛KOSHINO, Go教授諸言語部門
ロシア文学・文化史私の専門はロシアおよび旧ソ連地域の文学・文化史です。ロシア文化の起源は専らヨーロッパに求められますが、その歴史的な展開の中でアジアの諸地域をも含むようになりました。その意味で、冷戦の一方の主役であったソヴィエト連邦は、東洋と西洋にまたがるユーラシアの帝国でもありました。私の研究では、記憶政治、越境、文化翻訳などに着目しながら、複数の地域文化の比較を行います。ロシアという空間は、ヨーロッパとアジアの両方の文化において重要なコンタクト・ゾーンなのです。
-
 小林 薫KOBAYASHI, Kaoru准教授
小林 薫KOBAYASHI, Kaoru准教授諸言語部門
西洋古典学古代ギリシアの文学を研究の対象としています。特に紀元前5世紀のギリシア悲劇が、民主政アテナイという言説空間でどのような位置を占めていたかに関心があります。この他、古典文学の伝統の中で描かれる「客人歓待」「復讐」「嘆願」といった地中海的なテーマに興味を持っています。
-
国文学専攻
日本漢文学(近世・近代)江戸・明治時代の日本人が作った漢詩や漢文を研究しています。これまでは、今日忘れられている幕末・明治期の専門漢詩人の業績について再評価を試みるとともに、森鷗外や正岡子規などの近代の文学者と漢文学との関係について分析を行ってまいりました。現在は、漢籍の日本への流入状況や、日本漢詩におけるカノン形成の過程に着目しながら、戦前までの漢文文化の大きな流れについて考えています。また、近世文学における海外表象のあり方や、漱石など近代作家に関する史料考証にも関心を持っています。
-
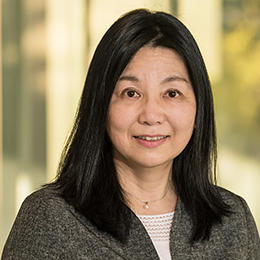 後藤 文子Goto, Fumiko教授goto@flet.keio.ac.jp
後藤 文子Goto, Fumiko教授goto@flet.keio.ac.jp美学美術史学専攻
西洋美術史ドイツ近代美術を中心として研究に取り組んでいます。とりわけ19世紀から20世紀への転換期ドイツにおいて社会変革思想と感性的創造行為が独特な仕方で接合した様相を重視し、美術、建築、庭園(造園、庭づくり)、デザイン、さらに身体運動(ダンス、体操)等の相互関連性について芸術学・デザイン学の立場から検討しています。20世紀初頭からドイツ国共和制期の芸術状況が近年の研究における重要な検討対象です。
-
 五味 知子GOMI, Tomoko准教授tomokowuwei@keio.jp
五味 知子GOMI, Tomoko准教授tomokowuwei@keio.jp東洋史学専攻
明清社会史、中国ジェンダー史私は、明末~清末の社会における庶民女性の生活について研究しています。庶民女性が自分自身で書き残した記録がないため、裁判史料や公文書に示された庶民女性にかかわる社会通念や倫理規範について検討しています。近年は、清末の新聞において、裁判関連の事柄がどのように報道されたかについても興味を持っています。
-
 阪井 裕一郎SAKAI, Yuichiro准教授
阪井 裕一郎SAKAI, Yuichiro准教授社会学専攻
家族社会学・歴史社会学私は、結婚・パートナーシップについての社会学的研究を進めてきました。主な内容は、結婚の歴史社会学的研究、事実婚についての質的社会調査、家族・パートナー関係の理論的研究です。脱標準化する家族や共同生活に関心を持っています。
-
 坂本 光Sakamoto, Hikaru教授hikaru.sakamoto@keio.jp
坂本 光Sakamoto, Hikaru教授hikaru.sakamoto@keio.jp英米文学専攻
近現代イギリス文学18世紀から20世紀初頭にいたる小説作品、特にゴシック文学 (恐怖文学) を研究しています。
-
 佐川 徹Sagawa, Toru教授sagawa@flet.keio.ac.jp
佐川 徹Sagawa, Toru教授sagawa@flet.keio.ac.jp人間科学専攻
人類学、アフリカ地域研究文化人類学的な視点から戦争と平和に関する研究を進めています。人びとはなぜ戦争に参加するのか、戦場でいかなる経験をしているのか、平和を形成・維持するためにどのような営みを続けているのか、といった問いを、フィールドワークにもとづいて検討してきました。最近はグローバル化と地域開発の問題、アフリカン・フードの展開にも関心を寄せています。
-
 佐々木 康之SASAKI, Yasuyuki准教授ssk0811@keio.jp
佐々木 康之SASAKI, Yasuyuki准教授ssk0811@keio.jp美学美術史学専攻
日本美術史日本の古代、中世仏教彫刻史を専門とし、主に平安時代の浄土教彫刻を研究対象としてきました。彫刻作品単体だけでなく、それを置く場を構成する絵画、工芸の各種表現や、さらには観者との関係に強い関心があります。また、美術館勤務の経験から、彫刻や工芸作品の展覧会での見せ方についても、一緒に考えていきたいと思います。
-
 佐藤 孝雄Sato, Takao教授sato@keio.jp
佐藤 孝雄Sato, Takao教授sato@keio.jp民族学考古学専攻
動物考古学、民族考古学人と自然の関係史を読み解くために、遺跡から出土する動物遺体の分析に取り組んでいます。文化と自然を包括的に捉え、第四紀の歴史を通観することに努めつつ、北海道や北部本州、シベリア、ベトナムでフィールドワークを重ねています。
-
 佐藤 恵SATO, Megumi准教授megumis@keio.jp
佐藤 恵SATO, Megumi准教授megumis@keio.jp独文学専攻
歴史語用論、ドイツ語史ことばの使い方から当時の社会や人間関係を読み解くような言語史研究に魅力を感じて、研究者になりました。例えば私はいま、モーツァルトの手紙やベートーヴェンの筆談帳を研究して、今から200年ほど前に書かれた言語データから当時の社会や書き手たちの人間関係を再構成するという研究をしています。
-
 清水 明子Shimizu, Akiko教授shimizua@flet.keio.ac.jp
清水 明子Shimizu, Akiko教授shimizua@flet.keio.ac.jp西洋史学専攻
ドイツ現代史・ユーゴスラヴィア史ナチズムがヨーロッパ周縁の多民族社会にもたらした支配体制の実態と地域の権力関係、社会変容を明らかにする研究を進めています。ドイツとバルカンにおける国民統合、「民族共同体」構築やネイション形成プロセスの解明につなげ、「国民国家」をめぐる議論にも向き合います。