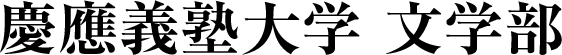- ホーム
-
教員
教員Faculty
名前/職位
専攻/専門領域/研究内容
-
 永崎 研宣NAGASAKI, Kiyonori教授
永崎 研宣NAGASAKI, Kiyonori教授図書館・情報学専攻
情報技術を用いた人文学における研究手法の改良情報技術を用いて人文学の研究手法を改良することに力を入れています。元々は仏典のテキストデータベース構築から始まり、SAT大蔵経テキストデータベースの構築を手がけつつ、お寺に入って貴重な資料のデジタル化のお手伝いなどもしてきましたが、そこから発展して、データの持続可能性と共有可能性に焦点をあてるようになり、Unicodeにおける仏典外字の登録や、人文学向けテキストの構造化に関わる国際デファクト標準であるText Encoding InitiativeガイドラインやWeb画像共有の国際デファクト標準であるIIIFの開発・普及や規格の策定などに取り組んできました。さらに近年はAIの活用にも取り組んでおり、TrOCRを用いた木版や手書き資料の自動文字認識や、専門的データとRAGを組み合わせた生成AIの精度向上に取り組んでいます。2024年度はこのテーマで国内の学会・研究会のみならず、台北、敦煌、ベルリン、ブエノスアイレス、ワシントンDC、UCバークリー、ウランバートル等で研究発表をしてきました。日本でもこういう研究テーマが広がっていくとありがたいと思っています。 一方で、海外のこの種の研究を日本に広めるための活動にも力を入れています。2024年4月に三田で仕事を始めてからは、韓国、カナダ、米国(2回)、オランダから来日したこの分野の研究者に、三田に来ていただいて講演会などを開催しました。 文部科学省としても、人文学のDXという事業を開始し、そのなかでもテキストデータモデルの構築に関わる部分を慶應義塾ミュージアム・コモンズが受託して研究活動を始めたところです。今後の人文学の行く末にご関心がおありのかたは、ぜひこの活動に首を突っ込んでみてください。意外に役立つ発見があるかもしれません。
-
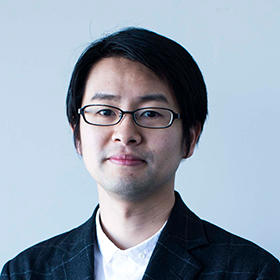 西尾 宇広NISHIO, Takahiro准教授nishio@keio.jp
西尾 宇広NISHIO, Takahiro准教授nishio@keio.jp独文学専攻
近代ドイツ文学ドイツの哲学者ユルゲン・ハーバーマスに代表される「公共圏」論に、文学研究の立場からアプローチを試みています。これまでは、フランス革命後の混乱の時代を生きたプロイセン人作家ハインリヒ・フォン・クライストを中心に、1800年頃のドイツ語圏の文化と政治をおもな考察対象としてきました。最近は「長い19世紀」の真ん中へと徐々に軸足を移しながら、文学やジャーナリズムを介して成立する広範な言論空間が社会のなかで担いうる公共的な役割について、歴史的な視野で考えています。目下、関心を持って取り組んでいるテーマは「嘘とフィクション」をめぐる問題圏です。
-
 西川 尚生Nishikawa, Hisao教授nishikawa.z3@keio.jp
西川 尚生Nishikawa, Hisao教授nishikawa.z3@keio.jp美学美術史学専攻
音楽学、西洋音楽史W. A. モーツァルトを中心とする古典派音楽の研究。モーツァルトの手稿譜の調査を通じて、作品をめぐる諸問題(成立過程、演奏実践、同時代の受容等)を解明しようと考えています。18世紀のウィーンとザルツブルクにおける宮廷楽団、劇場、公開演奏会、楽譜出版についても研究を進めています。
-
 西野 絢子Nishino, Ayako教授ayani@keio.jp
西野 絢子Nishino, Ayako教授ayani@keio.jp仏文学専攻
現代フランス文学・日仏演劇交流20世紀前半、劇場における諸芸術(劇・音楽・舞踊)の統合を試みたポール・クローデルが、能・歌舞伎など日本の伝統的な楽劇から受けた影響について研究しています。また、能をめぐる日仏の演劇交流の歴史にも関心を抱いています。
-
 野々瀬 浩司Nonose, Koji教授kononose@flet.keio.ac.jp
野々瀬 浩司Nonose, Koji教授kononose@flet.keio.ac.jp西洋史学専攻
スイス宗教改革史、農村社会史これまで宗教改革的な新しい神学が近世ヨーロッパ社会に与えた影響について、実証的に考察してきました。特にドイツ農民戦争期の抗議書を史料として用いて、平民が抱いていた「神の法」思想の分析を行い、16世紀のスイスや西南ドイツにおける農奴制問題と宗教改革運動との関わりを研究しました。最近では、宗教改革期の戦争観や都市と宗教改革の関係についての研究を開始しました。
-
 橋本 良一HASHIMOTO, Ryoichi助教ryoichi.hashimoto@keio.jp
橋本 良一HASHIMOTO, Ryoichi助教ryoichi.hashimoto@keio.jp英米文学専攻
近現代イギリス文学、詩と詩学19世紀イギリスの詩、特にアルフレッド・テニスンの詩を研究対象としています。詩学や引喩、翻訳、ノンセンス文学などに関心がありますが、特に詩における反復に興味があり、博士論文ではテニスンの詩における反復を扱いました。
-
 長谷川 敬Hasegawa, Takashi准教授takahase@flet.keio.ac.jp
長谷川 敬Hasegawa, Takashi准教授takahase@flet.keio.ac.jp西洋史学専攻
古代ローマ史(社会経済史)ローマ帝国西方地域、とりわけガリア・ゲルマニア諸属州(現在のフランス、スイス、ベネルクス3国、ドイツ西部・南西部にほぼ相当)の経済や社会について研究しています。私が特に関心を持っているのは、商人や職人たちがどのような人的ネットワークを構築していたか、ということであり、彼らが残した石碑(碑文)を主要史料として、考古学史料や地理学的情報も参照しながらその解明に取り組んでいます。
-
 長谷部 史彦Hasebe, Fumihiko教授manzala@keio.jp
長谷部 史彦Hasebe, Fumihiko教授manzala@keio.jp東洋史学専攻
中近世中東社会史、アラブ都市史、地中海交流史エジプト、シリア、アラビア半島を視野の中心に据え、アラブ地域の中近世史を研究してきました。現在は、オスマン帝国期とフランス占領期のエジプトにおける都市や村落の政治・社会・経済・文化の多角的な解明をめざして、地方都市マハッラ・クブラーのイスラーム法廷記録を読み解いています。また、近世カイロの無名の計量人が記した歴史書の研究も進めています。
-
 原田 亜希子HARADA, Akiko助教speranza03@keio.jp
原田 亜希子HARADA, Akiko助教speranza03@keio.jp諸言語部門
近世イタリア史、都市ローマ史、教皇史近世のイタリア、ローマの歴史を研究しています。中でも教皇の存在に注目し、カトリック世界の精神的トップであるだけでなく、ローマを中心とする中部イタリアの広大な領土を実際に統治する世俗君主でもあった教皇のもとに、近世のローマがどのように統治されていたのか、教皇と都市ローマとの関係を考察しています。ローマの特殊性を明らかにすると同時に、この時代の国家の一般的特質を見出すことも目指しています。
-
 バナード ピーターBERNARD, Peter准教授
バナード ピーターBERNARD, Peter准教授英米文学専攻
日本近代文学、比較文学、幻想文学、ゴシック論近代英米文学と日本近代文学における「田舎ゴシック」言説を研究対象として、泉鏡花やM・R・ジェイムズ、H・P・ラヴクラフトについて研究しています。また、近代日本におけるゴシック翻訳論という視点から日夏耿之介にも関心があります。
-
 平井 靖史HIRAI, Yasushi教授hiraiya@keio.jp
平井 靖史HIRAI, Yasushi教授hiraiya@keio.jp哲学専攻
時間と心の哲学。記憶の形而上学。ベルクソンおよびライプニッツを中心とする近現代哲学時間におけるマルチスケールという観点に着目し、延長と時制(テンス)のみならず相(アスペクト)を組み込んだ時間哲学を構築しつつ、それを用いて意識・心・自由・記憶といった哲学的諸問題へのアプローチを模索しています。伝統的な哲学テクストに含まれるアイデアを、現代の分析哲学や科学理論の枠組みから再解釈・再定式化することで、哲学史と哲学をより普遍的な思考のツールとすることに関心があります。
-
 福島 幸宏FUKUSHIMA, Yukihiro准教授fukusima-y@keio.jp
福島 幸宏FUKUSHIMA, Yukihiro准教授fukusima-y@keio.jp図書館・情報学専攻
図書館情報学・アーカイブズ・デジタルアーカイブ ・日本近現代史京都府立総合資料館・京都府立図書館、東京大学大学大学院情報学環特任准教授を経て、現職。京都府立総合資料館では、近代行政文書の文化財的修理・昭和戦前期資料の公開・京都市明細図の活用・東寺百合文書の記憶遺産登録・CC BYでのweb公開を担当し、Library of the Year 2014大賞を受賞。京都府立図書館では、サービス計画の策定・図書館協議会の設立・評価基準の検討・横断検索の高速化などを担当。知識情報基盤の構築やデジタルアーカイブなどについて研究。
-
 福田 弥Fukuda, Wataru教授wafukuda@flet.keio.ac.jp
福田 弥Fukuda, Wataru教授wafukuda@flet.keio.ac.jp美学美術史学専攻
音楽学、西洋音楽史19世紀ロマン主義の作曲家フランツ・リストの音楽、とりわけ宗教的作品が研究対象です。残された手稿譜や書簡などから、作品の成立過程、稿と編曲の関係、さらに作品を取り巻く環境などの解明に取り組んでいます。
-
 藤木 健二Fujiki, Kenji教授kfujiki@keio.jp
藤木 健二Fujiki, Kenji教授kfujiki@keio.jp東洋史学専攻
オスマン帝国史、中東都市社会史オスマン帝国期を中心とする前近代の中東諸都市において、人々がどのように生活していたかという問題に関心があります。現在は、都市民の多数を占める商人や職人に着目し、オスマン帝国期のイスタンブルを中心に商工民や同職組合について研究をしています。商工民の生活や同職組合の運営の実態を解明するため、主に未刊行史料であるイスラーム法廷記録から関連する事例を抽出し、それらの解読と分析を進めています。また、同様の問題関心から、当時の娯楽や消費文化、慈善・救貧活動・相互扶助などに関する研究にも取り組んでいます。
-
 藤野 陽平FUJINO, Yohei教授
藤野 陽平FUJINO, Yohei教授社会学専攻
文化人類学、東アジア地域研究台湾を中心に東アジアを対象としたエスノグラフィ調査を行っています。テーマとしては宗教を主たる対象としていますが、近年では植民地主義、ポスト植民地主義、民主主義、メディア、観光といったテーマにも関心を持っています。
-
 藤本 誠Fujimoto, Makoto准教授fujimoto@flet.keio.ac.jp
藤本 誠Fujimoto, Makoto准教授fujimoto@flet.keio.ac.jp日本史学専攻
日本古代史6世紀半ばに大陸・半島から国家的に受容された日本の仏教が,その後、何故古代社会に受容され,人々に信仰されたのかということについて、仏教思想や国家と社会との関係から研究しています。加えて,古代日本における仏教説話集の成立について、中国仏教書にみえる思想や表現との比較や、書物の受容の観点から考察を進めています。
-
自然科学部門
発生生物学、免疫生物学多細胞生物は、「自己」と「非自己」を識別し「非自己」を体から排除する免疫システムを例外なく備えています。「非自己」という存在は、「自己」という存在なしには成立し得ないため、免疫システムが正常に機能するためには、個体の発生過程で「自己」を確立する必要があります。では、この「自己」を確立するメカニズムは生物進化の過程でどのように獲得されていったのでしょうか?この問題を追求することで、「自己とは何か?」という哲学的な問いに対して、自然科学から面白い知見を提供したいと考えています。
-
 ブランクール ヴァンサンBrancourt, Vincent訪問教授(招聘)vbrancourt@hotmail.com
ブランクール ヴァンサンBrancourt, Vincent訪問教授(招聘)vbrancourt@hotmail.com仏文学専攻
フランス文学Récemment, parmi les question qui m'intéressent, je me suis notamment attaché à m'interroger sur la manière dont dans des œuvres de dramaturges modernes ou contemporains comme Giraudoux ou Koltès l'espace scénique se mue en espace imaginaire et la façon dont ces auteurs intègrent dans leur dramaturgie une réflexion sur le statut de cet《espace imaginaire》, en particulier autour de la question de la fascination.
***
Recently, my attention has been drawn into the work of modern and contemporary playwriters such as Giraudoux or Koltès, in particular reflecting upon how the stage space morphs into an imaginary space as well as how these authors include in their dramaturgic compositions, a reflection on the status of this “imaginary space”, notably focusing on the fascination aspect. -
 ベッカー アンドレアスBecker, Andreas訪問准教授(招聘)becker.andreas@posteo.de
ベッカー アンドレアスBecker, Andreas訪問准教授(招聘)becker.andreas@posteo.de独文学専攻
映画、メディア学目下のところ、小津安二郎の映画を手がかりに、日本映画と西洋映画の美学上の影響関係を研究しています。そのほかの研究領域としては、映画における時間表現、とりわけ低速度撮影と高速度撮影による表現可能性の問題があります。私の研究の理論的な基礎は、フッサールの現象学、ヴァルター・ベンヤミンの理論、そして比較美学です。
-
 細野 香里HOSONO, Kaori助教kaorihosono@keio.jp
細野 香里HOSONO, Kaori助教kaorihosono@keio.jp英米文学専攻
19世紀アメリカ文学・文化マーク・トウェイン(1835–1910)を中心に19世紀アメリカ文学を研究対象としてきました。最近はジョージ・リッパード(1822–1854)らによる南北戦争以前の扇情主義的文学作品における拡張主義の研究に取り組んでいます。
-
英米文学専攻
英語史、歴史言語学古英語から現代英語にかけての言語変化の諸相、および英語史の記述に関心があります。とりわけ言語変化の how と why を探ることに興味があります。なぜ英語の名詞複数形に -s がつくのかという疑問に目覚めてから何年も経ちますが、言語は不思議だらけですので、疑問が次から次へ湧き出てきて尽きることはありません。最近は REcord(名詞)と reCORD(動詞)のペアなどが示す「名前動後」の強勢パターンの歴史的発展や英語綴字史に関心を寄せています。