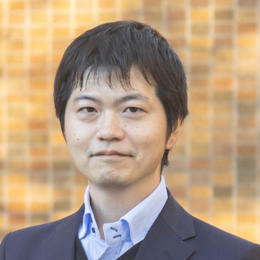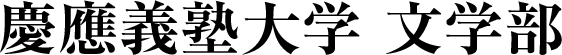- ホーム
-
教員
教員Faculty
名前/職位
専攻/専門領域/研究内容
-
日本史学専攻
クリオメトリクス(計量経済史),近代日本経済史・経営史,日本植民地経済史市場(market)とは取引所・法的規制など多様な組織・制度が基盤を構成し,価格形成を通じた財・サービスの配分を実現します。こうした市場の基盤的組織・制度に関する記述史料の歴史学的な定性分析と高頻度取引データによる時系列計量経済学的な定量分析を併用し,近代の「帝国日本」における市場の機能と稼働条件の通時的変容を分析しています。市場の役割を歴史的な視点から動態的に理解し,市場の機能向上に貢献可能な知見の獲得を目指しています。
-
 松倉 梨恵MATSUKURA, Rie助教lihui@flet.keio.ac.jp
松倉 梨恵MATSUKURA, Rie助教lihui@flet.keio.ac.jp中国文学専攻
中国現代文学女性作家の丁玲や廬隠を中心に、中国現代文学におけるジェンダー・セクシュアリティについて研究しています。
-
 松本 直樹Matsumoto, Naoki教授matsumoton@keio.jp
松本 直樹Matsumoto, Naoki教授matsumoton@keio.jp図書館・情報学専攻
図書館・情報学公立図書館の制度・経営を中心に研究しています。特に、外部環境との相互作用の中で公立図書館がどのように事業を形成しているかを、行政学等、学際的アプローチを使って明らかにしてきました。得られた知見をもとに、コミュニティの知の拠点としての図書館のあり方を探っていきたいと考えています。
-
民族学考古学専攻
西アジア・南アジア地域の考古学専門は西・南アジア地域における先史時代の考古学です。とくに人類が農耕・牧畜を始めてから、人口が徐々に増加していき、都市・文明社会が生まれるまでの期間に関心があります。この期間に人類はさまざまなモノ、さまざまな地域の人々と絡まり合いながら、さまざまな社会の「かたち」を模索し続けました。私はこの模索期間における社会変化を、遺跡から出土したモノをたよりに捉え直していきたいと考えています。 研究でモノと向き合うにあたっては、自然科学の諸分野と共同研究をおこない、モノからできるだけ多くの情報を引き出すとともに、近年の哲学、文化人類学の動向を踏まえ、モノをとおして歴史の見方をさらに広げていきたいと考えています。こうした方針のもと、イラン、イラク・クルディスタン、オマーン、パキスタンをフィールドとして、先史時代の集落や墓地の発掘調査、踏査をおこなっています。
-
 峯島 宏次MINESHIMA, Koji准教授minesima@abelard.flet.keio.ac.jp
峯島 宏次MINESHIMA, Koji准教授minesima@abelard.flet.keio.ac.jp哲学専攻
言語哲学、論理学、意味論・語用論現代の言語哲学と意味論・語用論の観点から、言語・論理・認知の接点にかかわる問題群を中心に研究を行なっています。また、言語学・計算機科学・認知科学など周辺分野との交流のもと、人間の言語理解の形式的・計算的なモデルを構築することに関心をもっています。
-
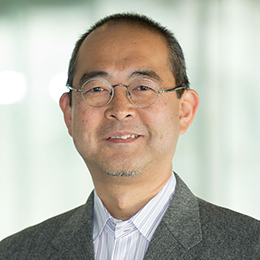 岑村 傑Minemura, Suguru教授sugurum@keio.jp
岑村 傑Minemura, Suguru教授sugurum@keio.jp仏文学専攻
近現代フランス文学20世紀の作家ジャン・ジュネの研究に軸足を置いていますが、ほかへの興味も尽きません。刑罰制度の表象については身を入れて調べていますし、「三面記事」、「帰還」、「告白」、「描写」など、ひとつの主題をめぐって複数の作品を読み解いていくことにも愛着をもっています。
-
 宮田 洋輔MIYATA, Yosuke助教miyayo@keio.jp
宮田 洋輔MIYATA, Yosuke助教miyayo@keio.jp図書館・情報学専攻
図書館・情報学現在は,図書館情報学分野を事例として,学問分野が形成されていく過程に量的・質的両方のアプローチから取り組んでいます。またメディアの利用やウェブに関する共同研究にも参加しています。
-
 望月 典子Mochizuki, Noriko教授nomoc@keio.jp
望月 典子Mochizuki, Noriko教授nomoc@keio.jp美学美術史学専攻
西洋美術史・芸術学17世紀フランス美術史・美術論。ニコラ・プッサン研究を中心に、プッサンの作品を規範として掲げた17世紀後半の王立絵画彫刻アカデミーにおける美術理論の確立とその変容に関心を持っています。画家の制作論、実際の作品とその受容、作品や画家を巡る言説、社会的文脈、美術コレクションなど、相互に絡み合う様々な要因を考察に加え、研究に取り組んでいます。
-
社会学専攻
社会学理論、社会学史、社会科学の哲学、知識社会学、(歴史)文化社会学、政治社会学、法社会学、世界社会論私の現在進行中の研究プロジェクトは以下の通りです。①ポスト・ポイエティック・パラダイムの研究:プラトン、アリストテレス以来の西洋思想の三つの軸は、制作(ポイエーシス)に定位した行為理解、制作物としての存在者理解、質的断絶のない、流れるものとしての時間(過去・現在・未来)理解です。社会学的思考も、その成立期にこの伝統 を受け継いでおり、例えば多くの行為理論で、行為の意味は制作物の意味をモデルに考えられています。ポスト・ポイエティック・パラダイムの研究はこの伝統的思考様式の相対化を目指します。②赦しと和解の社会学、③世界社会における民主制と権威主義の問題
-
 森元 規裕MORIMOTO, Norihiro助教
森元 規裕MORIMOTO, Norihiro助教仏文学専攻
17世紀フランス文学・思想近世フランスにおける活版印刷術の発展に伴い、「書物」という媒体がいかに作家の思考や技法を規定したかを考察しています。具体的には、神学や法学といった学知、あるいは論理学、修辞学、詩学といった諸学芸の伝達様式がどのように変化したかに関心があります。ルイ14世の孫の傅育官でもあったカンブレ大司教フェヌロンと教会史家クロード・フルリを主たる研究対象としています。
-
 諸星 妙MOROHOSHI, Tae助教(有期)tae_morohoshi@keio.jp
諸星 妙MOROHOSHI, Tae助教(有期)tae_morohoshi@keio.jp諸言語部門
スペイン美術史スペインの黄金世紀の美術について研究しています。特に初期セビーリャ時代のベラスケスのボデゴン画に興味があり、17世紀初頭のセビーリャにおける自然主義的絵画の起源とボデゴン画の関係を解明したいと考えています。同時代のスペインにおける絵画理論や絵画蒐集についても研究を進めています。
-
 山梨 あやYamanashi, Aya教授yamanasi@flet.keio.ac.jp
山梨 あやYamanashi, Aya教授yamanasi@flet.keio.ac.jp教育学専攻
日本教育史、社会教育史日本の近代化過程において、読書という行為が人間形成にどのように関わるのかを歴史的に検討することを研究課題としてきました。上記の研究課題に加え、現在、明治期から1970年代に至るまでの学校・家庭・地域の連絡・協力関係について、第二次世界大戦後の成人女性(主に「母親」)に対して「民主主義」や「民主化」といった新しい理念がどのように教育されていったのかについて研究を進めています。
-
 山道 佳子Yamamichi, Yoshiko教授yoshikoy@keio.jp
山道 佳子Yamamichi, Yoshiko教授yoshikoy@keio.jp西洋史学専攻
スペイン(カタルーニャ)近代史スペインの中でも独自の歴史・文化・言語を持つ地域(ネーション)のひとつであるカタルーニャの近代史を研究しています。ここ数年の研究テーマは、18世紀後半から19世紀初頭のバルセローナ市の絹織物及び絹に関わる手工業の職人の世界(仕事、家族、信仰)を、職人とその妻や寡婦の遺言書・死後財産目録・結婚契約書などの史料から再構築することです。なかでも特に現在は、ストッキング製造業者に焦点をあてて調べています。授業では、これまで勉強してきた都市形成、祭り、スポーツなど、カタルーニャの社会文化史に関わるさまざまテーマや、カタルーニャの独立運動の現状などを、広く紹介しています。
-
 吉永 壮介Yoshinaga, Sosuke教授yoshinaga@keio.jp
吉永 壮介Yoshinaga, Sosuke教授yoshinaga@keio.jp中国文学専攻
中国古典文学明代の白話小説『三国志演義』を中心に、正史・志怪小説・地誌等の伝承に見られる史実と虚構との揺らぎ、特にメディアによる伝播のあり方の相違という受容史に関心を持っています。また、古典通俗小説が現代サブカルチャーとして展開する様相にも興味を持っています。
-
 ヨッホ マルクスJoch, Markus教授joch@keio.jp
ヨッホ マルクスJoch, Markus教授joch@keio.jp独文学専攻
近現代ドイツ文学・文化学文学研究(Literaturwissenschaft)と文化研究(Kulturwissenschaft)とは密接に関連して発展してきています。私はこの立場を踏まえて、カルチュラル・スタディーズやブルデューの社会理論を援用し、近現代のドイツ文学を、文化や社会やメディアとの関係を重視しながら考察しています。転換点としての1945・1989年にも興味があります。
-
 若澤 佑典WAKAZAWA, Yusuke准教授yusuke.wakazawa@keio.jp
若澤 佑典WAKAZAWA, Yusuke准教授yusuke.wakazawa@keio.jp英米文学専攻
18世紀イギリスの文学・文化、スコットランド啓蒙思想、会話/対話としての哲学学部ではイギリス経験論やアメリカン・プラグマティズムといった英語圏の思想史を学び、「共感」や「驚き」といった日常生活の言葉でものを考え、書くことの重要性を実感しました。大学院からは、文学と哲学が交差する18世紀イギリスの言語空間にとりわけ魅せられ、専門分野としてきました。ポスドク以降は「おしゃべりの文化」から18世紀イギリスの文学・思想・絵画についてずっと考えています。とりわけ、会話・社交する存在としての人間像を提示し、当人もお話し好きだった哲学者/歴史家/文筆家デイヴィッド・ヒュームの著作や書簡が研究の主軸です。プロジェクト研究では18世紀東アジアの専門家たちと協働し、「グローバルな18世紀世界」像の構築を目指しています。
-
 和気 尚美WAKE, Naomi助教(有期)wake@keio.jp
和気 尚美WAKE, Naomi助教(有期)wake@keio.jp図書館・情報学専攻
図書館・情報学人種、民族、言語、宗教などの点で少数派とされる人と、公共図書館との関係について関心を持っています。これまでは主にインタビューや観察調査といった定性的な手法を用いて研究してきました。制度、図書館職員、利用者など異なる視座からアプローチすることで、公共図書館の実態と今後のあり方をより多角的に捉えていきたいと考えています。
-
 渡辺 丈彦Watanabe, Takehiko教授take@flet.keio.ac.jp
渡辺 丈彦Watanabe, Takehiko教授take@flet.keio.ac.jp民族学考古学専攻
旧石器考古学、日本古代史、文化財行政学東北日本を中心とした旧石器時代の石材原産地遺跡や洞穴遺跡の調査・研究を通じて、過去の人々と周囲の自然環境との関わりを明らかにすることが主要な研究テーマです。さらに時代は新しくなりますが、古代瓦磚の研究を通して古代都城・官衙の成立・発展過程を考えることも研究テーマの一つです。また、遺跡の発掘調査や研究の成果を、一般の方々にわかりやすく伝えるための埋蔵文化財保護行政の仕組み作りにも関心があります。
-
 渡邊 福太郎Watanabe, Fukutaro准教授watanabe@flet.keio.ac.jp
渡邊 福太郎Watanabe, Fukutaro准教授watanabe@flet.keio.ac.jp教育学専攻
教育哲学「言語」、「経験」、「変容」をキーワードに、現在は以下の研究テーマに取り組んでいます。(1) R・S・ピーターズを中心とする、創設期の分析的教育哲学の再評価と再構成の試み、(2) 斎藤喜博の授業論、武田常夫の授業記録の分析、(3)ウィトゲンシュタインの宗教哲学・宗教思想にかんする研究。